ピアスを開けたいと思っているけれど、どんな方法が一番いいのか迷っていませんか?
ニードルピアスは、従来のピアッサーよりも痛みが少なく、きれいなホールが作れると注目を集めているアイテムです。
でも実際にどこで買えるのか、安全なものはどれなのか、初めての方にはわからないことだらけですよね。
今回は、ニードルピアスの販売店舗について詳しく調査し、安心して購入できる場所をご紹介していきます。
先に結論:確実に買うならネットショップが安定です👇
ニードルピアスが売ってる場所はどこ?

ニードルピアスを探している方にとって気になるのが「一体どこで買えるの?」という疑問ですよね。
実は、ニードルピアスは医療機器扱いになるため、販売できる場所がかなり限られているんです。
ドンキホーテ
「ドンキに行けば何でも揃う」なんて言葉もあるくらい、豊富な品揃えで有名なドンキホーテ。
ピアス関連のアイテムも充実していそうな印象がありますが、ニードルピアスについてはどうでしょうか?
調査の結果、一部の店舗では取り扱いがあることが分かりました。
しかし、全ての店舗で販売しているわけではないのが現実です。店舗によって品揃えに差があるため、事前に電話で確認してから足を運ぶのが賢明ですね。
オンラインショップ(Amazon・楽天・Yahoo!ショッピング)
結論から言うと、ニードルピアスを確実に購入したいなら、オンラインショップが最も確実で便利な選択肢です。
Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要なECサイトでは、指定管理医療機器認証番号を取得した正規品を多数取り扱っています。
オンラインショップの最大の魅力は、商品詳細がしっかりと記載されていることです。
認証番号はもちろん、材質、太さ(ゲージ)、長さなどの仕様が明確に表示されているので、安心して購入できますよね。口コミやレビューも参考にできるため、実際に使用した人の声を聞けるのも大きなメリットです。
特に人気が高いのは以下のような製品です:
- ドクター・ニードルPro(滅菌済・医療用ステンレス)
- サージカルステンレス製ニードル
- 個別包装の滅菌ニードル
価格も実店舗と比べて競争が激しいため、お得に購入できることが多いんです。送料を含めても、交通費を考えると結果的に安く済むケースも少なくありません。
ピアススタジオ・専門店
プロにピアッシングをお任せするピアススタジオでは、当然ながら高品質なニードルを使用しています。
一部のスタジオでは、ニードル単体での販売も行っているんです。専門店ならではの品質管理と、プロのアドバイスが受けられるのが最大の魅力ですね。
ただし、価格は一般的なオンラインショップよりも高めに設定されていることが多いです。
また、取り扱い店舗数が限られているため、お住まいの地域によってはアクセスが困難な場合もあります。
ニードルピアスが売っていない場所はどこ?

ニードルピアスを探す際に、つい足を向けてしまいそうな場所でも、実際には取り扱いがないことが多いんです。
100円ショップ(ダイソー・セリア・キャンドゥ)
「最近の100均は何でも揃う」なんて話をよく聞きますが、ニードルピアスに関しては残念ながら取り扱いがありません。
ダイソー、セリア、キャンドゥなど主要な100円ショップを調査しましたが、どこでもニードルピアスの販売は確認できませんでした。
薬局・ドラッグストア
薬局やドラッグストアなら医療用品を扱っているから、きっとニードルピアスも置いてありそうですよね?
でも実際に調査してみると、残念ながらほとんどの店舗では取り扱いがありませんでした。
マツモトキヨシ、ウエルシア、スギ薬局、セイムス、コスモスなど主要なドラッグストアを確認しましたが、ニードルピアスの販売は確認できなかったんです。
一般的な雑貨店・アクセサリーショップ
街でよく見かけるアクセサリーショップや雑貨店では、残念ながらニードルピアスの取り扱いはほとんどありません。
Claire’s(クレアーズ)のような海外発のアクセサリーチェーンでも、日本国内ではニードルピアスの販売は行っていないのが現状です。
コンビニエンスストア
最近のコンビニは本当に便利で、医薬品から化粧品まで幅広い商品を取り扱っていますよね。
でも、ニードルピアスについては、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンなど主要なコンビニチェーンすべてで取り扱いがありません。
ホームセンター
「工具から日用品まで何でも揃う」ホームセンターでも、ニードルピアスの取り扱いはありません。
カインズ、コメリ、ホーマック、コーナンなど主要なホームセンターを確認しましたが、どこでも販売は確認できませんでした。
家電量販店
ヨドバシカメラ、ビックカメラ、ヤマダ電機などの家電量販店では、最近は生活雑貨も扱っていることが多いですが、ニードルピアスの販売はありません。
医療機器の販売許可が必要なため、家電量販店での取り扱いは現実的ではないんです。
ニードルピアスの種類について
ニードルピアスを購入する前に知っておきたいのが、種類や規格の違いです。「ニードルならどれでも同じ」と思っていませんか?
実は、太さ(ゲージ)、材質、滅菌処理の有無など、様々な違いがあるんです。
太さ(ゲージ)による分類
ニードルピアスの太さは「ゲージ(G)」という単位で表記されます。数字が小さいほど太く、大きいほど細くなるのが特徴です。初めて聞く方には少し分かりにくいかもしれませんが、覚えてしまえば簡単ですよ。
最も一般的なのが14Gと16Gです。14Gは約1.6mm、16Gは約1.2mmの太さになります。耳たぶの場合は16Gまたは18G(約1.0mm)が適していることが多く、軟骨部分は14Gが推奨されることが多いんです。
- 18G(約1.0mm):耳たぶ、細い部位向け
- 16G(約1.2mm):耳たぶ、初心者におすすめ
- 14G(約1.6mm):軟骨、しっかりしたホール作りに
- 12G(約2.0mm):上級者向け、太いピアス用
太いニードルほどホールが安定しやすいメリットがありますが、痛みや腫れも強くなる傾向があります。初心者の方は16Gから始めるのが無難ですね。
材質による違い
ニードルピアスの材質選びは、安全性に直結する重要なポイントです。最も安全とされているのが、医療用サージカルステンレス(SUS316L)です。
この材質は金属アレルギーを起こしにくく、錆びにくいという特徴があります。
医療現場でも実際に使用されている材質なので、安心感が違いますよね。
価格は一般的なステンレスよりも高めになりますが、安全性を考えると投資する価値は十分にあります。特に金属アレルギーの心配がある方は、必ず医療用グレードの材質を選ぶようにしましょう。
一方で、価格の安い海外製品の中には、材質が不明確なものや、有害な物質を含む可能性があるものも存在します。
「安かろう悪かろう」という言葉もありますが、体に直接刺すものだからこそ、品質にはこだわりたいものです。
滅菌処理の有無
ニードルピアスを選ぶ際に絶対に確認したいのが、滅菌処理の有無です。「滅菌済み」と表記されている製品は、製造後に特殊な処理を施して細菌を完全に除去しているんです。
個別包装されているものがほとんどで、使用直前まで清潔な状態が保たれています。
滅菌処理がされていないニードルを使用すると、感染症のリスクが高まってしまいます。自分で消毒液に浸しても、完全な滅菌は困難なんです。
少し価格は高くなりますが、安全性を考えると滅菌済みの製品を選ぶのが賢明でしょう。
また、滅菌済み製品には有効期限が設定されています。古い製品は滅菌効果が低下している可能性があるため、購入時は製造日や有効期限も必ずチェックしてくださいね。
長さの選び方
ニードルの長さは、開けたい部位の厚みに合わせて選ぶ必要があります。短すぎると貫通しきらず、長すぎると扱いにくくなってしまうんです。一般的な耳たぶの場合は、25mm〜38mm程度の長さが適しています。
軟骨部分は耳たぶよりも厚みがあることが多いため、やや長めのニードルが必要になることもあります。また、腫れることを考慮して、実際の厚みよりも少し長めを選ぶのがコツです。
初心者の方は、「どの長さを選べば良いか分からない」という悩みを抱えがちです。そんな時は、複数の長さがセットになった商品を選ぶか、オンラインショップの商品説明や口コミを参考にすると良いでしょう。
よくある質問
- ニードルピアスとピアッサーの違いは何ですか?
-
ニードルピアスは中空の針で穴を開ける方法で、ピアッサーよりも痛みが少なく、きれいなホールができやすいのが特徴です。また、ホールの安定も比較的早く、感染リスクも低いとされています。ただし、使用には慣れが必要で、初心者には少し難しい面もあります。
- ニードルピアスはどこで購入するのが一番安全ですか?
-
最も安全で確実なのはAmazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなどの大手オンラインショップです。指定管理医療機器認証番号が明記された正規品を多数取り扱っており、商品詳細も充実しています。口コミやレビューも参考にできるため、初心者の方にも安心してお勧めできます。
- 初心者におすすめのニードルの太さは?
-
初心者の方には16G(約1.2mm)がおすすめです。耳たぶなら16Gまたは18G、軟骨なら14Gが一般的です。太いほどホールは安定しやすいですが、痛みや腫れも強くなるため、最初は細めから始めて慣れてから太いものに挑戦するのが良いでしょう。
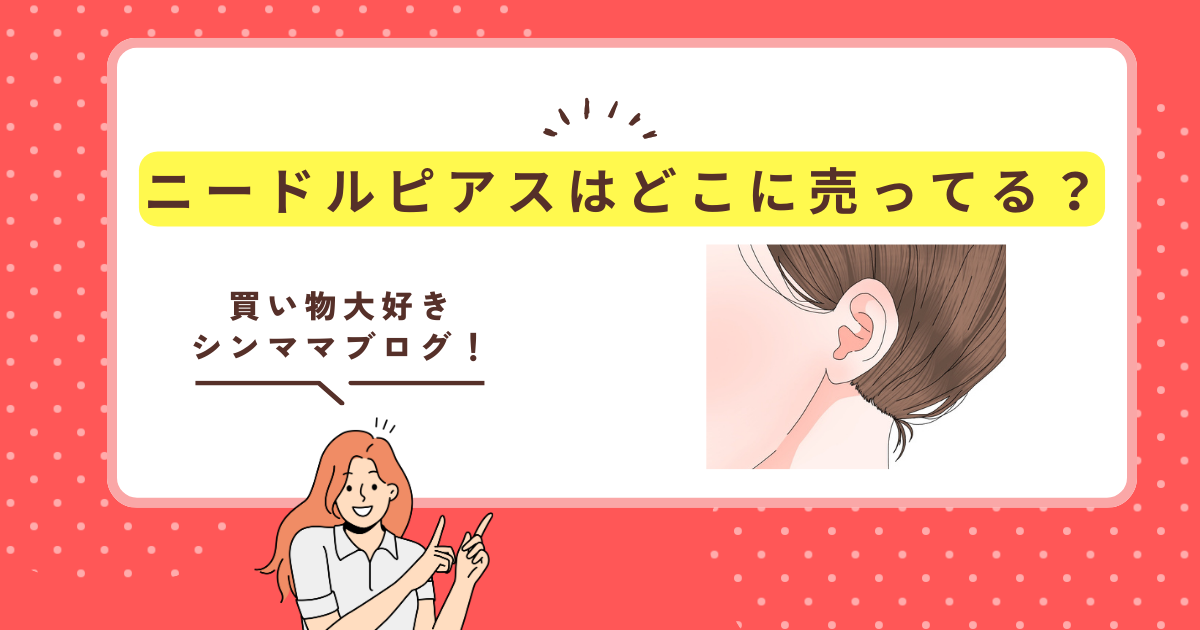


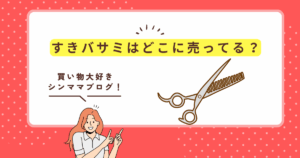

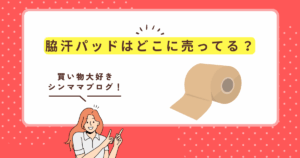
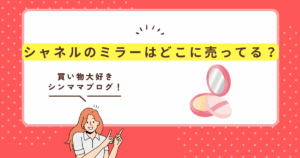
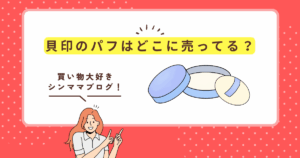
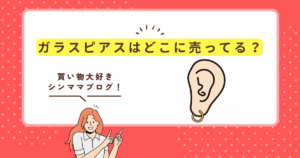

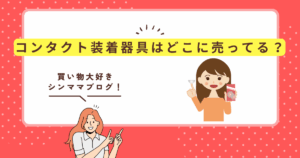
コメント